|
内容目次 |
|
| ● |
はじめに:「がんに罹りやすいという遺伝的な特徴」,「遺伝性疾患としてのがん」について突きつめて考える
(平沢 晃)
|
|
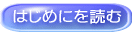 |
|
| ●Ⅰ.総論 |
| 1. |
遺伝性腫瘍総論
(三木義男) |
|
遺伝性腫瘍は,親から子へ受け継がれる遺伝子の病的バリアントによって生じる腫瘍性疾患で,このような個人の特定は,がんの予防,早期介入および個別のマネジメントに非常に重要である。遺伝性腫瘍研究は遺伝性および散発性がんの理解を深め,原因遺伝子の機能不全を標的とした抗腫瘍剤の開発が進み,この治療を受けた遺伝性がん患者に予後の改善がみられている。また,生殖細胞系列バリアント探索に遺伝子パネルによる遺伝学的検査が推奨され,すでに欧米では,この結果を日常のがん治療に統合し利用するシステム構築が進められている。
|
|
| 2. |
遺伝性腫瘍の遺伝学的検査と品質保証
(宮地勇人) |
|
近年,遺伝学的検査に基づく遺伝性腫瘍の診療は大きく変貌している。次世代シークエンサーを用いたマルチプレックス遺伝学的検査やがん遺伝子パネル検査は,遺伝性腫瘍の患者個別に最も適切な医学的管理の選択を可能とする。早期診断,サーベイランスと予防に加えて,分子標的治療へと展開している。遺伝子関連・染色体検査を国際水準にするため,検体検査の精度の確保に係る医療法等の一部改正が2018年12月1日に施行された。これにともない,遺伝子関連検査のためのISO 15189施設認定プログラムや外部精度管理調査など環境・体制整備が進められている。
|
|
| 3. |
遺伝カウンセリング総論
(山内泰子) |
|
遺伝カウンセリングでは,クライエントが自身に適した意思決定をするために,遺伝カウンセリング担当者が情報提供や心理社会的支援を行う。クライエントが直面している思いを傾聴することが肝要である。込み入った問題を明らかにし,具体的に提示することが遺伝カウンセリングの大きな機能である。これには言語・非言語のコミュニケーションスキルが求められる。クライエントが語る来談理由をよく傾聴して,対応することが肝要である。患者やその家族は,遺伝性疾患のリスクと向き合い,疾患に対処している。
|
|
| 4. |
バリアントの表記と解釈
(井本逸勢) |
|
配列バリアントの一貫性のある曖昧さのない記述は,ヒトゲノム解析に関する報告や情報共有,特に遺伝学的検査による診断結果の評価や伝達に不可欠である。HGVS(Human Genome Variation Society)によって提案された配列バリアント命名法システムは,広く採用され,改訂を繰り返しながら国際的に認められた標準規格に発展しており,臨床現場においても標準命名法としてその使用が推奨される。一方,バリアントの臨床的意義づけは,2015年に提案されたACMG(American College of Medical Genetics and Genomics)/AMP(Association for Molecular Pathology)ガイドラインを基本に5段階のカテゴリーに分類する方法が広く受け入れられ,一貫性,透明性のある判定のために仕様を更新しながら使われている。バリアントの病原性の分類は連続性のある概念であり,常に更新される最新の情報に基づき再分類する必要がある。
|
|
| 5. |
遺伝性消化器がん 概説
(母里淑子・石田秀行) |
|
一般に原因遺伝子が明らかにされており,一般集団より明らかに腫瘍が好発しやすい個人あるいは家系に発生する腫瘍に対し,遺伝性腫瘍の名称が用いられる。遺伝性腫瘍の特徴の一つとして多臓器発がんが認められ,特に消化器に発がん傾向が強い場合に遺伝性消化器がんと呼称することがある。
本稿では,成人の消化器に腫瘍性病変を好発する主な遺伝性腫瘍(一部家族性腫瘍を含む)の種類,疾患概要,診断を中心に概説する。
|
|
| 6. |
遺伝性婦人科がん 概説
(小林佑介・青木大輔) |
|
遺伝性腫瘍はすでに原因遺伝子が明らかとなっているものだけでも多岐にわたるが,なかでも遺伝性乳癌卵巣癌(BRCA1/2 遺伝子),Lynch症候群(DNAミスマッチ修復遺伝子),Peutz-Jeghers症候群(STK11/LKB1 遺伝子),Cowden症候群(PTEN 遺伝子)は関連腫瘍として子宮頸癌,子宮体癌,卵巣癌を引き起こすリスクが知られており,婦人科がんと関連のある遺伝性腫瘍として,この4疾患をその臨床的特徴とともに熟知しておくことが重要である。また,婦人科遺伝性がん診療を取り巻く社会環境が大きく変化してきていることに留意し,最新の臨床情報を得ながら日々の診療に当たる必要がある。
|
|
| 7. |
遺伝性乳癌 概説
(中村清吾) |
|
すべてのがんは,遺伝子変異が原因で発症するが,そのすべてが遺伝性ではない。乳癌全体の5〜10%が遺伝性といわれている。2020年4月より,遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC:hereditary breast and ovarian cancer)が疑われる乳癌もしくは卵巣癌患者に,BRCA検査(遺伝学的検査)が保険適用となり,さらに対側の予防的乳房切除,すなわちリスク低減乳房切除術(RRM:risk reduction mastectomy)および卵管卵巣の予防的切除,すなわちリスク低減卵管卵巣切除術(RRSO:risk reduction salpingo-oophrectomy),術後サーベイランスとしての乳房MRIも保険適用となった。保険診療上,遺伝性乳癌が認知された出発点といえる。また,日本におけるHBOCに対するデータベースも整備され,(社)日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構(JOHBOC)の元に,NCD(National Clinical Database)に登録され,各種研究に用いられている。今後は,未発症陽性者への対応に拡充していく(ハイリスク検診や化学予防を含む)とともに,遺伝性乳癌の原因となる他の遺伝子群へのきめ細やかな対応を診療ガイドライン内に整備していくことが必要であろう。
|
|
| 8. |
遺伝性泌尿器腫瘍 概説
(蓮見壽史・浜之上はるか・矢尾正祐) |
|
歴史的に遺伝性腎癌を中心に行われてきた遺伝性泌尿器腫瘍の研究が,近年の次世代シーケンサーの登場により,腎盂尿管癌や前立腺癌などの様々ながん種へ広げられ,泌尿器腫瘍における生殖細胞系列バリアントとその腫瘍化機構の解明に注目が集まっている。遺伝性泌尿器腫瘍の病態解明は,家系全体の健康管理に役立つと同時に,散発性泌尿器腫瘍に対する新規薬剤や診断技術の開発へ応用することができる。日常診療において相当数の遺伝性泌尿器腫瘍が見逃されていると推測され,本邦における遺伝性泌尿器腫瘍の全体像はいまだ明らかではない。われわれは遺伝性泌尿器腫瘍における最新情報を日々更新しながら,候補症例に対し適切に遺伝カウンセリングを提供できるよう体制を整備する必要がある。
|
|
| 9. |
小児の遺伝性腫瘍 概説
(中山佳子) |
|
がんゲノム医療の普及に伴い,小児においても遺伝性腫瘍と診断される患者の増加が見込まれる。原因となる遺伝子の病的バリアントが判明した症例では,将来罹患する可能性の高い疾患を想定した適切なサーベイランスが施行でき,予後の改善が期待される。その一方で小児期発症のがんを扱うことの特殊性への配慮は不可欠であり,遺伝カウンセリングの果たす役割は大きい。本稿では小児の遺伝性腫瘍の代表的な疾患を示し,近年公開された診療ガイドラインを引用しながら,小児の遺伝性腫瘍の概要を述べる。
|
|
| ●Ⅱ.疾患各論 |
| 1.HBOC |
|
1) |
遺伝性乳癌卵巣癌(Hereditary breast and ovarian cancer:HBOC)
(平沢 晃・浦川優作) |
|
|
遺伝性乳癌卵巣癌(hereditary breast and ovarian cancer:HBOC)はBRCA1/2 生殖細胞系列病的バリアントに起因する遺伝性疾患で,乳癌,卵巣癌,膵癌,前立腺癌などの腫瘍発症リスクが高い。HBOC家系に対してはBRCA1/2 遺伝学的検査を行い,がん予防,予後予測,個別化がん治療選択を通して,がん死低減に結びつけることが可能となる。本稿ではHBOC総論として,BRCA1/2 遺伝子とBRCA1/2タンパクの特性,わが国におけるHBOC診療の歴史,および医療システムとしての現状と課題を概説する。
|
|
|
2) |
乳腺領域
(大住省三) |
|
|
HBOCの方は乳癌超高リスクの方である。女性の場合,生涯で70%程度の乳癌リスクを有している。また,HBOCの男性も乳癌高リスクで,特にBRCA2 のキャリアで乳癌高リスクである。このような方々では乳癌死を避けるための対策が必要である。この高い乳癌リスクに対しての対策としては,主にMRIを用いたサーベイランス,タモキシフェンを用いた化学予防,リスク低減乳房切除術などがある。また,HBOCで乳癌に罹患した場合の治療について,特に女性の場合で多くの研究がされてきている。本論文ではこれらの現状について述べる。
|
|
|
3) |
卵巣癌に対するHBOCの診断と治療
(関根正幸・西野幸治・榎本隆之) |
|
|
卵巣癌に対するゲノム医療は,BRCA1/2 遺伝子の生殖細胞系列病的バリアント(gBRCAm )を原因とする遺伝性乳癌卵巣癌(hereditary breast and ovarian cancer:HBOC)を主な対象として行われた臨床試験により,PARP阻害薬の有効性が証明され大きく変貌を遂げた。PARP阻害薬は,今では臓器横断的に相同組換え修復異常(homologous recombination deficiency:HRD)を示すがんに対して有効性が示されている。再発卵巣癌の維持療法においては,PARP阻害薬の感受性を予測する臨床的なサロゲートマーカーとしてプラチナ感受性が用いられ,さらに初回治療における維持療法を中心としたコンパニオン診断としてgBRCA1/2 遺伝子検査と腫瘍におけるMyriad myChoice HRD検査が保険適応となった。さらに,HBOCの乳癌あるいは卵巣癌患者に対する予防診療が2020年4月より保険収載され,HBOCに対する診断と治療が日々変化している状況となっている。本稿ではHBOCの卵巣癌患者をターゲットとしたゲノム医療と,ゲノム情報に基づく先制医療の現状と展望について解説する。
|
|
|
4) |
泌尿器科領域のHBOC:前立腺癌とHBOCの深い関係性
(小坂威雄) |
|
|
遺伝的な前立腺癌リスクとして,生殖細胞系列病的バリアントを有する遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)が前立腺癌と深く関係することは知られてきた。本邦においてもHBOCに関連するBRCA1/2 変異陽性前立腺癌患者が確かに存在することが明らかになった。近年,特に前立腺癌においては,BRCA1/2 の生殖細胞系列病的バリアントのみならず,体細胞病的バリアントとして,転移や薬剤耐性に関連することが明らかになってきている。2020年12月に薬剤耐性去勢抵抗性前立腺癌に対して,PARP阻害剤が適応となった現在,HBOCをめぐる日常臨床は様変わりしつつある。本稿では前立腺癌とHBOCの深い関係性について概説する。
|
|
|
5) |
膵癌
(尾阪将人) |
|
|
膵腺癌(PDAC)は,依然として5年生存率は9%を下回る治療が困難な悪性腫瘍の一つである。近年,膵癌のゲノム研究により,BRCA1/2 病的バリアントは,膵癌の発症・治療ターゲットの一つとして注目されている。BRCA1/2 とPALB2 の生殖細胞系列病的バリアントは,膵癌患者の約5〜9%で検出され,相同性修復欠損(HRD)を引き起こす可能性が指摘されている。HRDをもつ膵癌は,DNA損傷を引き起こす白金製剤が期待されている。さらに,PARP阻害剤は,HRD膵癌を治療するための有効な非細胞毒性アプローチとして登場した。BRCA とPALB2 に加えて,ATM やRAD51 などの相同性DNA修復経路に関与する他の遺伝子の生殖細胞系列病的バリアントも,「BRCAness」表現型をもつ患者やDNA修復経路の体細胞変異と同様に,潜在的な標的と期待されている。本稿では,PDACにおけるHRDの現在のバイオマーカーと新たなバイオマーカー,治療法,およびそれらに関連する課題について説明する。
|
|
| 2.Lynch症候群 |
|
1) |
Lynch症候群(総論)
(池上恒雄・古川洋一) |
|
|
Lynch症候群は,大腸癌を中心に様々な臓器に腫瘍を発生する常染色体優性遺伝形式の遺伝性腫瘍の一つである。原因遺伝子は,主にMLH1,MSH2,MSH6,PMS2 であるが,病的バリアントが存在する遺伝子により表現型に多少の違いがある。これらの原因遺伝子はミスマッチ修復に関わるタンパク質をコードしており,ミスマッチ修復機能欠損が腫瘍発生・進展に関与している。腫瘍細胞には多数の体細胞変異が蓄積し,多くの場合,高頻度マイクロサテライト不安定性を示す。また,この腫瘍は免疫チェックポイント阻害剤の効果が高いことも特徴の一つである。
|
|
|
2) |
消化器領域
(赤木 究) |
|
|
Lynch症候群の原因遺伝子はミスマッチ修復遺伝子であり,すべての細胞のゲノム維持機構として重要な役割を果たしているため,その機能喪失はゲノムの塩基配列に新たな変化をもたらし,その蓄積はがん発症の要因となる。Lynch症候群の関連がんには,多くの消化器がんが含まれる。その中でも大腸癌は最もリスクが高いがんとして,多くの知見が得られているが,その他の消化器がんは発症リスクがそれほど高くないため,いまだ不明な部分が多い。エビデンスに基づいた医療提供のためにも,さらなる症例を収集し,知見を集める必要がある。
|
|
|
3) |
婦人科領域におけるLynch症候群
(進 伸幸・河原井麗正・木原真紀・岡田智志・片岡史夫・田中宏一) |
|
|
婦人科領域におけるLynch症候群関連腫瘍として子宮内膜癌と卵巣癌が挙げられる。その病態はミスマッチ修復(MMR)遺伝子の異常であり,子宮内膜癌は全臓器の腫瘍の中でマイクロサテライト不安定性(MSI)を示す頻度が約30%と最も高い。臨床病理学的な二つの診断基準,腫瘍組織におけるMSI検査またはMMR遺伝子タンパクに対する免疫染色,MMR遺伝子の生殖細胞系列病的バリアントの同定,により診断される。治療は通常の子宮内膜癌,卵巣癌の治療ガイドラインに基づくが,治療抵抗性のMSI陽性例に対しては免疫チェックポイント阻害薬が保険収載され,新たな治療分野の幕開けを迎え,MSIについて習熟しておく必要がある。
|
|
|
4) |
その他の腫瘍(消化器・婦人科領域以外)
(山本英喜) |
|
|
消化器領域,婦人科領域以外のLynch症候群の関連がんには,上部尿路上皮癌,脳腫瘍などがある。いずれも希少がんであるが,Lynch症候群での発症リスクは高くなる。特にMSH2 の生殖細胞系列病的バリアント陽性例では上部尿路上皮癌,脳腫瘍の発症リスクが高く,注意を要する。脳腫瘍はLynch症候群の死因となる主要な関連がんである。上部尿路上皮癌では患者の約5%はLynch症候群といわれており,ユニバーサルスクリーニングの合理性が提唱されている。Lynch症候群では脂腺癌などの皮膚腫瘍の合併もある。
|
|
| 3. |
MEN1
(鈴木眞一) |
|
MEN1は副甲状腺,膵,下垂体を中心に複数の内分泌臓器に発生する遺伝性疾患である。副甲状腺機能亢進症を95%に認め,膵・消化管神経内分泌腫瘍(GEPNET)と下垂体腫瘍は約半数に認め,さらに副腎皮質腫瘍や胸腺気管支の神経内分泌腫瘍(NET)などを認める。MEN1 バリアントは約80%に認めるが,他は大欠失やphenocopyがある。副甲状腺腫瘍やGEPNETでは多腺・多発が多いことから,診断治療を考慮する。さらに予後はGEPNETと胸腺NETが影響している。最近は乳癌や静脈血栓塞栓症の発生増加が認められ,褐色細胞腫が合併した症例も出てきている。
|
|
| 4. |
多発性内分泌腫瘍症2型
(櫻井晃洋) |
|
多発性内分泌腫瘍症2型(MEN2)は多くの遺伝性腫瘍の中で例外的にがん遺伝子の機能獲得型変異が原因となる疾患である。それゆえ遺伝型と表現型(臨床像)には極めて強い相関があり,原因遺伝子RET の遺伝学的検査は非常に有用性が高く,診療に必須の情報となっている。本稿では,MEN2の原因や臨床像,治療と遺伝医療について,その概略を解説する。臨床的な詳細については成書や他の総説を参照していただきたい。
|
|
| 5. |
遺伝性網膜芽細胞腫
(鈴木茂伸) |
|
網膜芽細胞腫は小児の眼球内に生じる悪性腫瘍であり,RB1 遺伝子変異に起因する。眼内腫瘍は主に臨床診断に基づき治療方針が決定され,5年生存率は95%,約半数の眼球が温存されている。遺伝性腫瘍の視点では,RB1 遺伝子の生殖細胞系列バリアントによる遺伝であり,両側発症,三側性網膜芽細胞腫,二次がんが問題となる。発端者の遺伝学的検査は保険診療として行われるが,非発症者の保因者診断は自費診療で行う必要がある。
|
|
| 6. |
Li-Fraumeni症候群
(熊本忠史) |
|
Li-Fraumeni症候群(LFS)は,生殖細胞系列TP53 病的バリアントに起因し,常染色体優性遺伝する遺伝性腫瘍で,高浸透率,多重がんを特徴とする。発症する頻度が高い,乳癌,骨肉腫,副腎皮質癌,脳腫瘍,軟部肉腫をLFSのコア腫瘍と呼ぶが,LFSでは血液腫瘍,上皮性腫瘍などあらゆる種類のがんが発生する。また,退形成亜型横紋筋肉腫や副腎皮質癌など家族歴がなくてもLFSを疑うがん種がある。LFSの診断・診療は対象者に重大な心理的・身体的負担がかかるが,がんサーベイランスにより予後が改善する可能性がある。
|
|
| 7. |
FAP・AFAP・GAPPS(APC-associated polyposis condition)
(檜井孝夫) |
|
家族性大腸腺腫症(FAP)の原因遺伝子APC に起因する遺伝性腫瘍として大腸病変を主徴とするFAP,AFAPと胃病変を主徴とするGAPPSがある。大腸腺腫密度によってFAP(密生型),FAP(非密生型)とAFAPに分類されるが,大腸病変に対する外科的治療計画はFAPとAFAPで分けて考慮し,大腸外随伴病変に対してはいずれも長期的管理が肝要となる。胃底腺ポリポーシスを主徴とするGAPPSを背景とする胃癌は悪性度が高いため,胃病変の初回鑑別が重要となる。本稿では,APC関連ポリポーシスの特徴,遺伝学的検査の意義,鑑別診断と管理法について解説する。
|
|
| 8. |
von Hippel-Lindau病
(矢尾正祐・蓮見壽史・近藤慶一・浜之上はるか) |
|
von Hippel-Lindau(VHL)病は,VHL 遺伝子の生殖細胞系列のヘテロ接合性病的バリアントにより発症する常染色体優性遺伝性の腫瘍症候群で,網膜・中枢神経系の血管芽腫や淡明細胞腎癌を含む多臓器の腫瘍性病変を好発する。合併病変の治療は基本的には散発例のものと同様であるが,VHL病ではより早期から発症を繰り返すため,各疾患の特性をよく理解し,適切なサーベイランスと全身のQOLおよび罹患臓器の機能を最大限温存しつつ,一生涯にわたる疾患コントロールをめざすことが目標となる。
|
|
| 9. |
褐色細胞腫・パラガングリオーマ
(與那嶺正人・竹越一博) |
|
褐色細胞腫・パラガングリオーマ(PPGL)は生殖細胞系列バリアントを高頻度に有する神経内分泌腫瘍であり,変異遺伝子により表現型が異なる。PPGLを有するすべての患者に遺伝子解析を考慮するが,実施する際には臨床的意義と限界を共有し,十分な遺伝カウンセリングが必須である。多数のドライバー遺伝子が存在するため,次世代シーケンサーを用いた遺伝子パネルが推奨されている。変異遺伝子に応じた発端者や未発症血縁者のフォローアップが求められる。今後,遺伝学的クラスタリングに基づいた転移性PPGLに対する個別化医療の発展が期待される。
|
|
| 10. |
Cowden症候群/PTEN過誤腫症候群
(高山哲治・寺前智史・田中久美子・六車直樹) |
|
Cowden症候群/PTEN過誤腫症候群は,PTEN遺伝子の生殖細胞系列病的バリアントにより生じる常染色体優性遺伝性疾患である。皮膚,粘膜消化管,乳腺,甲状腺,泌尿生殖器などに過誤腫性病変を多発する。悪性腫瘍を合併するリスクが高く,乳癌,甲状腺癌,大腸癌の順に高く,子宮内膜癌や腎癌などの発症リスクも高い。がんの治療方針は,原則として散発性のがんに準じるが,同時性や異時性の発がんも少なくないことを考慮する必要がある。これらのがんは予後を規定する可能性が高いことから,本症候群を適切に診断し,適切にがんのサーベイランスを行うことが重要である。
|
|
| 11. |
Peutz-Jeghers症候群
(山口達郎・高雄暁成) |
|
Peutz-Jeghers症候群は,セリンスレオニンキナーゼタンパクをコードするSTK11 遺伝子の生殖細胞系列病的バリアントを原因とする常染色体優性遺伝性疾患である。食道を除く全消化管の過誤腫性ポリポーシスと皮膚・粘膜の色素沈着を特徴とする。消化管や乳腺,膵,子宮などに悪性腫瘍が好発するため,生涯にわたるサーベイランスが必要である。小児慢性特定疾病対策の対象疾患にもなっており,本稿では,Peutz-Jeghers症候群のサーベイランス上,押さえておきたいポイントについて概説する。
|
|
| 12. |
若年性ポリポーシス症候群
(田中屋宏爾・石田秀行・近 範泰・青木秀樹) |
|
若年性ポリポーシス症候群は,がん抑制遺伝子であるSMAD4 またはBMPR1A の生殖細胞系列病的バリアントを原因とする常染色体優性遺伝性疾患である。消化管の過誤腫性ポリポーシスと悪性腫瘍の合併を特徴とする。ポリープは,多くが20歳までに大腸に発生するが,胃,小腸にも発生し,ポリープ数も5〜100個以上と個人差がある。若年成人に消化器がんを発生するリスクが高く,日本人例の大腸癌生涯リスクは51%,胃癌生涯リスクは73%と報告されている。SMAD4 キャリアでは遺伝性出血性毛細血管拡張症を合併する。
|
|
| 13. |
Birt-Hogg-Dube(BHD)症候群
(古屋充子) |
|
Birt-Hogg-Dub?(BHD)症候群は腎腫瘍を主徴の一つとする単一遺伝子病で,ここ20年で国内外の診療研究情報が飛躍的に進化した。確定診断は遺伝学的検査によって原因遺伝子であるFLCN の病的バリアントを特定することが望ましい。生命予後やQOLは腎腫瘍に左右されるため,正しい知見に基づいた診療が求められる。本稿では,国内外で蓄積された臨床病理的知見をもとにBHD症候群の三主徴を中心に概説する。希少疾患であるため,疑い例に遭遇した場合の相談先なども記載する。
|
|
| 14. |
遺伝性びまん性胃癌
(椙村春彦・山田英孝・岩泉守哉・野村幸世) |
|
2019年に開催されたInternational Gastric Cancer Linkage Consortiumで,わが国のような胃癌の高頻度発生国も含めた遺伝性びまん性胃癌の疾患概念や遺伝子検査の絞り込み基準(ガイドライン),病理学的特徴や検索の原則などの議論があった。lobular typeの乳癌が家系に共存することから,同一疾患として扱うべきであるという見解やCTNNA1 の病的バリアントも含めて共通のmolecular pathwayに起因する疾患として認識すべきである(CDH1 associated cancerなど)といった意見もあった。本邦や韓国などではdiffuse type(びまん性)の胃癌という認識よりJapanese Classification Systemにあるsigを用いて絞り込んだほうがよい。がん遺伝子パネル,口蓋口唇裂といったphenotype,direct-to-consumer testといわれる商業的な遺伝子検査(本邦では医学的影響力の強い多型は搭載されていないという理解であるが)が契機になり発見される可能性も予想されている。
|
|
| ●Ⅲ.診療各論 |
| 1. |
腫瘍領域の遺伝カウンセリング
(田辺記子) |
|
遺伝子関連検査の拡大に伴い,腫瘍領域の遺伝カウンセリングは多様化しており,①遺伝性腫瘍診断を目的とする遺伝学的検査と,②個別化治療を目的とする遺伝子関連検査(腫瘍組織の検査,生殖細胞系列の検査の両方)がある。すなわち,①として「遺伝性腫瘍に関する相談・診断を主目的とする場面」,「多遺伝子パネル検査を実施する場面」,②として「治療選択目的の検査から生殖細胞系列病的バリアントが認められた/疑われた場面」などがある。個別化治療に端を発する遺伝学的検査を含めて,個人が遺伝性腫瘍と診断された場合,その人の状況に応じてがんの早期発見・早期治療の機会を提供することが必要となり,血縁者にも遺伝医療が必要となる。遺伝性腫瘍は,高頻度であること,早期発見・早期治療の機会を提供できるものも多いこと,世代をわたった対応が求められることが多い。クライエントの個別状況に応じた適切な遺伝カウンセリングの提供が求められる。
|
|
| 2. |
がんの臨床で役立つ家系図
(赤間孝典) |
|
がんの臨床で扱う家族歴は,各職種の限られた時間と場所で効率的に聴取され,各職種が共通認識できる情報として記録されることが重要である。「家族歴に関係なく遺伝学的検査を行う」臨床場面が増えた現在も,家族歴の利用価値がなくなることはなく,遺伝医療を提供するならば,家族歴聴取の必要性は不変である。
今回は,がんの臨床場面で家族歴を正しく共有できるように,家族歴と家系図についてご紹介する。
|
|
| 3. |
遺伝性腫瘍の患者と家族への看護
(村上好恵) |
|
遺伝性腫瘍は,多臓器にわたり同時性・異時性にがんを発症するという特徴があるため,患者は生涯にわたり医療機関への受診が必要となる。しかし遺伝性腫瘍に対する治療は,遺伝性ゆえの特別なことはなく,がんに対する通常の手術療法・薬物療法・放射線療法と同じである。したがって看護師は,日頃からがん患者に対して行っている身体的・心理的・社会的側面のアセスメントとケアを,遺伝性腫瘍の患者および家族に対しても同様に提供することを期待されている。
|
|
| 4. |
遺伝性腫瘍と生殖医療
(佐々木愛子・髙江正道・西垣昌和) |
|
遺伝性腫瘍の病的バリアント保因女性に対し,実施を検討すべき医学的ケアは多岐にわたる。これらのうち,どの医療が実際に選択できるかどうかは時代とともに変遷する可能性があるため,医療ケア担当者は日本での現状を正確に知る必要がある。対象となる患者(クライアント)が前もって将来の人生設計を立案できるよう,腫瘍の発生の有無にかかわらず生殖年齢に達した段階で,生殖領域における遺伝カウンセリングの機会が与えられるべきと考える。
|
|
|
|
|
1) |
PARP阻害薬
(松本光史) |
|
|
PARP阻害薬はDNAの一本鎖切断修復の阻害を行うことで,すでにDNAの二本鎖切断修復阻害が生じている腫瘍細胞に殺細胞作用を発揮する。当初はDNA障害作用のある薬剤や放射線治療の増感剤としての開発が先行していたが,オラパリブ単剤での第1相試験において生殖細胞系列のBRCA1/2 病的バリアントを有する患者への抗腫瘍効果が認められたことを契機に合成致死(synthetic lethality)の概念が提唱され,遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)関連がんでの開発が加速した。本稿では各がん種でのPARP阻害薬の位置づけとポイントとなる情報について簡潔にまとめる。
|
|
|
2) |
免疫チェックポイント阻害薬
(下平秀樹) |
|
|
免疫チェックポイント阻害薬(ICI)の登場により,がんの薬物療法は革新的な進歩を遂げた。高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-H)あるいはDNAミスマッチ修復タンパク質の発現欠損(dMMR)を示すがんにおいて,ICIは有効性が高いことが示され,本邦でも臓器横断的に保険適用となった。MSIやMMRの免疫組織染色は,ICIのバイオマーカーであるとともに,リンチ症候群のスクリーニング検査の意義もあるため,ICIによる治療を行ううえでは,リンチ症候群および遺伝性腫瘍に関する理解が必要とされる。
|
|
| 6. |
遺伝性腫瘍の画像診断
(田中高志・生口俊浩・平木隆夫・金澤 右) |
|
CT(computed tomography,コンピュータ断層撮影)やMRI(magnetic resonance imaging,核磁気共鳴画像),核医学検査など,近年の画像診断技術の進歩もあり,遺伝性腫瘍の患者において,より小さな病変の検出・診断が可能となってきている。加えて,遺伝性腫瘍症候群においては,放射線被ばくによる発がんや,遺伝性腫瘍でみられうる画像パターンの認識も重要で,近年の放射線医学関連のアップデートも踏まえ,理解しておく必要がある。
|
|
| 7. |
遺伝性腫瘍の病理診断
(桂田由佳・津田 均) |
|
多くの遺伝性腫瘍は,散発性腫瘍に比べ若年発症,同時性・異時性に多発する傾向がある。一部の遺伝性腫瘍は,特徴的な組織像を呈することもある。多臓器を横断的に診断する病理医は,遺伝性腫瘍の特徴,組織像に関して知識を有しておくことは重要である。また,Lynch症候群でのミスマッチ修復タンパクに対する免疫染色など,遺伝性腫瘍診断のスクリーニングを病理検査で実施することも可能となっている。乳癌または卵巣癌既発症の遺伝性乳癌卵巣癌に対するリスク低減乳房切除術やリスク低減卵管卵巣切除術が保険収載され,リスク低減手術検体に対する病理学的検索を適切に行うことも病理医に求められている。
|
|
| ●Ⅳ.倫理・法・社会的問題(ELSI) |
| 1. |
遺伝情報の取り扱い−遺伝子例外主義からの脱却
(小杉眞司) |
|
遺伝情報を特別なものとして,通常の診療記録とは別に取り扱うことがかなりの医療機関で実施されているが,これには「遺伝子例外主義」の考え方や日本医学会による「遺伝学的検査・診断に関するガイドライン」(2011年)の記載が影響していると考えられる。すべての医療関係者は遺伝情報の特性を十分理解したうえで,厳格な守秘義務が課されている医療情報の一部としての遺伝情報を適切に共有し,取り扱うことによって,患者・クライアントに適切な遺伝医療を提供するとともに,医療関係者がもつ内なる遺伝差別を払拭する努力を行うべきである。
|
|
| 2. |
リスク低減手術をめぐる倫理的課題
(竹下 啓) |
|
2020年4月,乳癌あるいは卵巣癌を発症した遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)患者に対するリスク低減手術が保険適用となり,今後普及が進むと考えられる。既発症のがんに治療を行わなければ進行して致死的となるのが確実だが,リスク低減手術を受けない場合の不利益は不確実であることが特徴である。医療・ケア担当者は,医学的適応だけでなく,それぞれの患者が自分の価値観や周囲の状況に基づき適切にリスク低減手術について意思決定をできるよう支援することが求められる。今後HBOCと診断される患者の増加に伴い,がん未発症患者への対応や着床前診断などの生殖補助医療へのアクセスなどが課題となるだろう。
|
|
| 3. |
生命保険に関する現状と課題
(横野 恵) |
|
生命保険における不利益に対する懸念は,患者・市民が遺伝学的検査やゲノム研究への参加を躊躇する要因の一つとされる。ゲノム情報に基づく差別は許されないという理念は国際的合意を得ているが,本邦ではそれを担保するための制度が整備されていない。
ゲノム情報の取り扱いにおいては,①取得・共有の制限等によりゲノム情報そのものを保護する(情報保護)とともに,②ゲノム情報に基づく不利益な取り扱いを防止すること(差別禁止)が重要である。本邦で差別禁止のルールが未整備であることはゲノム情報の取り扱いに必要以上に慎重にならざるを得ない要因ともなっている。差別禁止ルールの確立が望まれる。
|
|
| 4. |
ゲノム医療と患者・市民参画(PPI)
(中田はる佳) |
|
ゲノム医療の推進にあたり,患者・市民参画(patient and public involvement:PPI)の必要性が広く認識されている。がんゲノム医療におけるPPIの実践として,がん遺伝子パネル検査の説明文書(モデル文書)や一般向け情報ウェブサイト作成時に「患者査読」が行われた。この実践から,PPIを行うにあたり患者・市民と出会う場をつくること,また患者・市民との継続的な関係構築と新しい視点を取り入れることのバランスが今後の課題と考えられた。ゲノム医療の恩恵を受ける立場の患者・市民の視点が欠けることのないよう,PPIの実践をさらに進めることが重要である。
|
|
| 5. |
ゲノム医療と国内外におけるバイオバンク事情
(吉田雅幸) |
|
医学の進歩は様々な疾患の診断や治療を可能としてきたが,このような医学の進歩には,それまでの医学研究の成果が大きく貢献している。最近の医学研究には,患者や健康な方々の試料(血液,組織,DNAなど)や情報(カルテ情報,健診情報など)の利用が必須となり,従来よりも多くの試料や情報が必要となっている。このような状況に対処するために,患者や一般の方々の試料や情報を一括管理し,将来の医学研究に利用するための「バイオバンク」の設置が国内外で進んでいる。本章では,特にゲノム医療の分野の発展,領域拡大とそれに貢献するバイオバンクの現状について解説する。
|
|
| ●Ⅴ.最新の話題,制度,情報 |
| 1.最新の話題 |
|
1) |
がんゲノム医療
(福田博政・河野隆志) |
|
|
日本のがんゲノム情報の集約・管理・利活用を図るための機関として,がんゲノム情報管理センター(C-CAT)が設置され,2019年6月より保険適用された二つのがん遺伝子パネル検査・受検者の臨床情報およびゲノム情報のC-CATレポジトリーへの登録が始まった。登録される情報には,がん遺伝子パネル検査で同定される患者の生殖細胞系列バリアントの情報も含まれている。C-CATでは,同定されるバリアントの解釈・臨床的意義づけ・国内臨床試験情報などを記載したC-CAT調査結果を作成することによりゲノム医療を支援している。診療現場でのレポジトリーデータの利用を支援するためのシステムおよび研究機関や企業の研究者が二次利活用するためのシステムの構築も進めている。また本邦では,リキッドバイオプシーを含む新たなパネル検査の開発や国主導の全ゲノム解析を基盤とするゲノム医療プログラムが進行中である。
|
|
|
2) |
がんゲノム医療で同定されるGermline findingsの取り扱い
(平田 真) |
|
|
がん遺伝子パネル検査の主目的は,体細胞バリアント解析による治療方針の策定である。しかし,同時に多数の遺伝子を解析するため,腫瘍由来の体細胞変異のみならず,生殖細胞系列所見を得ることがある。生殖細胞系列所見は本人のがん発症リスクを知るだけでなく,血縁者への遺伝可能性,がん発症リスク評価につながる重要な情報である。しかし,検査の主目的とは異なる所見となることも多いため,事前の説明と検出後の説明や対応が重要であり,主治医と遺伝の専門家との連携が不可欠である。本稿では,がん遺伝子パネル検査で検出される生殖細胞系列由来のバリアント評価の留意点や対応の実際について概説する。
|
|
|
3) |
がんゲノム医療で同定される生殖細胞系列バリアントに関する用語とその変遷
(浦川優作) |
|
|
がんゲノム医療は,腫瘍組織を用いて多数の遺伝子を解析し,検出された遺伝子に合わせた治療をすることが目的の一つであるが,同時に生殖細胞系列由来が疑われる遺伝子のバリアントが検出される場合がある。旧来そのようなバリアントは偶発的所見や二次的所見と呼ばれてきた。しかし,特にがん遺伝子パネル検査では解析する遺伝子があらかじめ決まっていることや,検出された遺伝子の情報をより有効に活用する重要性に焦点が当たっており,germline findingsと呼ばれるようになってきた。このような用語の変遷について解説する。
|
|
|
4) |
多遺伝子パネル検査の利活用の実際
(吉田玲子) |
|
|
多遺伝子パネル検査(multi-gene panel testing:MGP testing)を行うことにより,病的バリアント検出率が増加し,がん治療,がん予防の対象が確実に拡がることが証明され,遺伝性腫瘍の既往歴・家族歴などから限られた遺伝子を検査する時代からMGP testingが推奨される時代となった。しかし,一般臨床で活用するには意義不明なバリアント(VUS)に対する問題や,腫瘍の遺伝医療を取り巻く医療社会的な問題にも取り組んでいく必要がある。
|
|
|
5) |
遺伝性腫瘍に関する保険診療の最新の動向と課題
(櫻井晃洋) |
|
|
遺伝性腫瘍に関する診療,特に診断を目的とした遺伝学的検査は長らく自費診療によって行われてきたが,2016年にRB1 とRET の遺伝学的検査が保険収載され,2020年には遺伝性乳癌卵巣癌(hereditary breast and ovarian cancer:HBOC)において,診断目的の遺伝学的検査のほか,発症者に対する未発症部位のサーベイランスやリスク低減手術も保険適用となった。これは遺伝性腫瘍診療において画期的なことと言えるが,すでにいくつかの新たな課題も明らかとなっている。遺伝性腫瘍は遺伝情報に基づく先制医療実装のモデルとなる疾患群であり,特にHBOCはその代表と言える。今回の診療報酬改定は,これからのわが国における遺伝性腫瘍診療のみならず,遺伝医療全体のあり方を考える契機となるものである。
|
|
|
6) |
遺伝教育とがん教育をめぐる課題
(渡邉 淳) |
|
|
がん診療において,遺伝子関連検査,遺伝学的検査を実施する機会が増えている。これらの検査の対象はがん患者全体に広がり,遺伝医療・ゲノム医療とのつながりや関わりが一般化しつつある。医療人においても,患者・家族においても,正しい「ヒトの遺伝」リテラシーの向上が求められる。一方で,成人前の教育,初等・中等教育では,「ヒトの遺伝」を取り上げる機会はほとんどなかった。ここ数年で,がん教育が初等・中等教育に導入される。がん教育は,「ヒトの遺伝」リテラシー向上の転換点になると考える。
本稿では,がん教育における「ヒトの遺伝」の位置づけを紹介し,今後の課題について言及する。
|
|
|
7) |
遺伝性腫瘍に関する国内外ガイドライン
(植木有紗) |
|
|
ガイドラインとは,最新かつ最善の治療法を常時把握し続けることを補助する目的のツールである。その内容は,国内外のエビデンスを蓄積し,現時点で最も標準的と考えられる治療法を提示したもので,強制力をもつものではないことを理解し,賢く利活用するべきである。特に遺伝性腫瘍関連でのガイドラインの目的としては,散発性腫瘍の中から遺伝性腫瘍の可能性が疑われることなく適切な医療提供の場を逸しないために,一般臨床医への知識の普及が大切である。本稿では国内外の各種ガイドラインの概要を解説する。
|
|
|
8) |
ゲノム・データベースとその活用
(田辺真彦・織田克利) |
|
|
遺伝性腫瘍の確定診断では生殖細胞系列遺伝子検査(遺伝学的検査)が行われる。がん遺伝子パネル検査では,がんゲノム情報に基づく治療可能性探索を目的として腫瘍組織の遺伝子検査が行われるが,生殖細胞系列バリアントの可能性が明らかとなる場合がある。遺伝子検査で検出されるバリアントについて,遺伝性腫瘍の責任遺伝子として確実であるか,あるいは治療標的となりうるかという臨床的意義を正確に評価することは極めて重要である。本稿では,遺伝性腫瘍医療およびがんゲノム医療に有用な各種データベースを紹介する。
|
|
|
9) |
遺伝性腎癌に対するアブレーション治療
(生口俊浩・平木隆夫・金澤 右) |
|
|
von Hippel-Lindau病,Birt-Hogg-Dub?症候群では繰り返し腎癌が発生し,治療においては腫瘍の根治と腎機能温存のバランスを考慮した戦略が必要となる。従来3cmを超えた際に切除が行われていたが,近年では「繰り返しの治療が可能」,「高い腫瘍制御」,「腎機能温存」の条件を満たすアブレーション治療がわが国でもこれら遺伝性腎癌に対して行われている。代表的なアブレーション治療として,わが国では凍結治療とラジオ波焼灼術が行われており,遺伝性腎癌の治療法の一選択肢として知っておくべきと思われる。
|
|
| 2.遺伝性腫瘍に関連した人材育成と認定制度・連絡会議等 |
|
1) |
臨床遺伝専門医制度について
(蒔田芳男) |
|
|
臨床遺伝専門医制度の成立の経緯,制度の目標,現状の課題を概説した。現在,臨床遺伝専門医制度委員会は,日本専門医機構認定のサブスペシャルティ領域専門医をめざして活動を行っている。
|
|
|
2) |
遺伝性腫瘍専門医制度
(田中屋宏爾・石田秀行) |
|
|
日本遺伝性腫瘍学会は,人材育成のため1998年からセミナー,2012年から家族性腫瘍コーディネーター・カウンセラー制度,そして2017年から遺伝性腫瘍専門医制度を運用してきた。専門医は,遺伝性腫瘍のマネジメントや遺伝カウンセリングはもとより,がんの一般的な疫学,コンパニオン診断や,がんゲノムプロファイリング検査など,遺伝学と腫瘍学に関する広範な知識と診療経験が求められる。今後,がんの一般臨床においても対応が求められる遺伝性腫瘍に関し,チーム医療における中心的な役割を果たしていくことが期待される。
|
|
|
3) |
認定遺伝カウンセラー®制度
(小杉眞司) |
|
|
認定遺伝カウンセラー®は,日本人類遺伝学会と日本遺伝カウンセリング学会が共同で2005年より認定している資格であり,2021年4月現在,294名が認定されている。国民に信頼される高度な専門性をもたせるため,米国と同様に修士課程相当での教育を課している。認定遺伝カウンセラーになるには,認定遺伝カウンセラー制度委員会が承認した,認定遺伝カウンセラー養成課程(現在23校)を修了し,認定試験に合格する必要がある。
|
|
|
4) |
遺伝看護専門看護師制度
(武田祐子) |
|
|
遺伝/ゲノム医療の発展に伴い,医療者が知識をもち,患者・家族を支えていく,裾野の広い医療提供体制が求められる。看護師は,様々な場面において役割を担っていくことが期待されるが,多くは知識不足を感じている。
遺伝看護専門看護師は,高い看護実践力とともに,相談,調整,倫理調整,教育,研究の六つの機能を有する。大学院修士課程で養成され,日本看護協会の審査を経て認定される。
遺伝/ゲノム医療提供体制の構築,遺伝医療チームの一員としての活動,そして遺伝/ゲノム看護の実践と質向上のための教育的役割への期待は大きい。
|
|
|
5) |
日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構と施設認定事業
(中村清吾) |
|
|
日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構は,日本乳癌学会,日本産科婦人科学会,日本人類遺伝学会が共同して設立された。活動の骨子は,診療施設の認定,遺伝性乳癌卵巣癌(HBOC)に関する教育研修,HBOCの患者等の登録,HBOCに関する調査研究などである。また,HBOC診療を行う施設を「基幹施設」,「連携施設」,「協力施設」の三つに区分して施設認定を行い,どの施設に行けばどのような医療サービスを受けることができるか公表し,HBOC診療体制の整備に努めている。
|
|
|
6) |
全国遺伝子医療部門連絡会議
(小杉眞司) |
|
|
全国遺伝子医療部門連絡会議は,大学病院等の医療機関の遺伝子医療部門の連携を保ち,学術的・社会的事柄に関する情報交換,ならびに構成員相互の意見交換を図り,遺伝子医療の発展に寄与することを目的としている。学会の枠を超えて遺伝子医療の実務に関する話題を現場の担当者がフランクに意見交換する場として位置づけられている。年1回の会議では講演と代表者ワークショップが行われ,その他に遺伝子医療施設検索システムの提供,GeneReviews JapanおよびNGSD(Next Generation Super Doctor)プロジェクトのサポートなどの活動も実施している。
|
|
|
7) |
ジェネティックエキスパート制度
(小杉眞司) |
|
|
ジェネティックエキスパートは日本遺伝子診療学会が認定する資格で,医療におけるヒトゲノムを対象とした遺伝子関連検査の解釈などを中心のスキルとするわが国唯一のヒトゲノムインフォマティシャン資格である。2015年より認定が開始され,2020年4月現在34名が認定されている。ゲノム医療の時代に臨床遺伝専門医や認定遺伝カウンセラー®のスキルアップの資格として適切と考えられる。
|
|
| 3.情報サイト |
|
1) |
関連学会,各種セミナー,当事者会,情報サイトなど
(二川摩周) |
|
|
遺伝性腫瘍診療には遺伝医学の知識や臓器横断的ながんの専門知識が必要不可欠であるが,これらの情報は目まぐるしく進歩するため日頃から学術集会や情報サイトで最新の知識を収集し,診療に活かすことが求められる。遺伝性腫瘍に従事する機会が少ない,あるいはこれから従事する予定の医療従事者にとっては,各種学会などが主催するセミナーやロールプレイが遺伝医療にふれる機会となる。
|
|
| ●索引 |