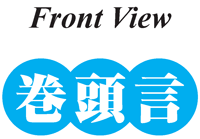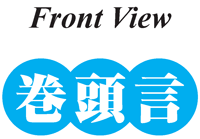2023年6月,日本で初めて「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」が制定された。この法律は,すべての国民が安心して質の高いゲノム医療を受けられるようにすることを目的としたものであり,今後はこの法律の理念に基づき,具体的な施策が進められていくと考えられる。
遺伝情報は個人を特定できる可能性があるため,個人情報保護法において「要配慮個人情報」として保護されている。また,その取り扱いにおいては医学的・社会的・倫理的な観点からも細心の注意が求められ,多くの分野でガイドラインが策定されている。特に産婦人科領域における遺伝子解析では,通常の遺伝情報の取り扱いに加えて生命倫理的な課題も伴うため,そうした複雑な背景や多様な意見が存在することを理解したうえで,診療や研究に取り組む姿勢が重要である。
出生前遺伝学的検査には,医学的・社会的・倫理的な配慮が必要な課題が多くある。そのため,検査の実施にあたっては「適切な遺伝カウンセリング」が不可欠である。出生前に行われる遺伝学的検査には以下のような検査が含まれる。スクリーニング検査(非確定検査)として行われる母体血清マーカー検査,胎児超音波マーカー検査,コンバインド検査(血清&超音波マーカー),非侵襲性出生前遺伝学的検査(non
invasive prenatal test:NIPT)と,診断的検査(確定検査)として施行される絨毛検査,羊水検査,胎児超音波精密検査がある。これらの検査によって「何がわかるのか」,「何がわからないのか」を妊婦や家族に対して十分に説明し,そのうえで検査を受けるかどうかの意思決定を支援する遺伝カウンセリングの重要性がますます高まっている。
さらに,近年の全ゲノム解析技術の進歩により,より詳細な遺伝情報の取得が可能になっており,将来的には単一遺伝子疾患や多因子疾患のリスク評価も視野に入ってきている。こうした科学的進展は,出生前検査を単なる異常の有無を判断する手段から,個別化医療への入り口へと進化させる可能性を秘めている。
日本でNIPTが導入された2013年からすでに12年が経過した。導入当初から,NIPTは社会的な議論を呼び起こしたが,2016年以降,不適切と考えられるNIPTの提供が広がりを見せた。その対策として,「NIPT等の出生前検査に関する情報提供及び施設(医療機関・検査分析機関)認証の指針」に基づき,出生前検査認証制度等運営委員会の主導により制度整備が進められた。しかしながら,制度が整ったにもかかわらず,不適切とされるNIPTは依然として行われており,その結果に対して不安を抱える妊婦や家族が少なくない。
また遺伝カウンセリング体制においても,地域や施設間での格差が問題となっている。出生前遺伝学的検査は,単に検査を行うだけではなく,その結果に基づいた丁寧な説明と適切な支援が必要不可欠である。しかし,遺伝医療に精通した医師や認定遺伝カウンセラーが不足している地域では,妊婦が十分な理解のもとで意思決定を行うことが難しい現状がある。
さらに検査を希望しても,医療機関へのアクセスが困難な状況も存在し,情報と選択肢の不平等を助長している。こうした状況を改善するためには,教育の重要性も忘れてはならない。遺伝や妊娠のこと,出生前検査に関する基礎知識を,学校教育や市民講座などを通じて広く普及させ,社会全体で命の多様性やその価値について考える土壌を育む必要がある。
出生前遺伝学的検査は,医学的に有用であると同時に,家族にとって大切な選択肢となり得るものである。しかし,その利用には高度な倫理的配慮と社会全体の理解・支援が不可欠である。日本がこの技術を真に人間的かつ社会的に受容できるかたちで発展させていくためには,法制度の整備,医療体制の充実,そして市民の意識啓発が一体となって進められることが求められる。命のあり方を深く見つめ直す中で,私たち一人ひとりが「どのような社会を望むのか」を考えることが,今まさに必要とされている。
|