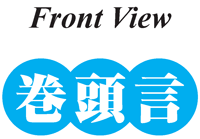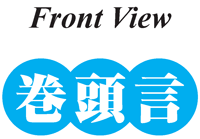筆者は精神科診療の現場で,当事者・家族から現在の診断・治療法の限界に関するもどかしさ,その解決を願う思いを伺うことがあり,解決につながる精神医学研究の成果達成を目指すことの重要性を日々実感している。加えて,筆者は複数の当事者・家族会に関わり,アウトリーチ活動とともに当事者・家族との診療,研究,医学教育に関する意見交換を実施してきた。例えば,ライフステージ依存的に多様な精神疾患と心疾患をはじめとする多様な臓器の疾患のリスクである22q11.2欠失症候群のご家族から,「22q11.2欠失という発症の原因がわかっているのだから,様々な精神疾患がどうして起こるかを突き止め,食い止める方法の開発を! 心臓が悪くても使える治療法の開発を!」との思いを伺った。
こういった経験を基に,筆者は当事者・家族の精神医学研究に関する意見聴取と,当事者・家族を対象としたアンケート調査を行ってきた。なお,この意見聴取およびアンケート調査の実施にあたり,当事者・家族会の協力を得て,その準備段階から当事者・家族に関与を依頼し,当事者・家族の率直な意見集約に努めた。
その結果,1022名の当事者・家族から回答を得て,当事者・家族が発展を望む分野について確認したところ,「病気の原因や,病気の仕組みを明らかにする研究(72%)」の発展を望む声が最も多く,次いで「新しい治療法の開発(69%)」,「効果が高く副作用の少ない薬の開発(68%)」を望む声が多かった(中村由嘉子,尾崎紀夫,他:精神神経学雑誌,印刷中)。さらに,本書にもご寄稿いただいた夏苅郁子先生から,「『100人の理解者・支援者よりも,母を治してくれる1錠の薬が欲しい』が,患者・家族としての本当の願いであった。原因が分からない病気ゆえに,精神疾患への偏見は解消されていない。当事者・家族は『創薬』への期待を諦めるわけにはいきません!」との思いを伺った(夏苅郁子:精神神経学雑誌
122号,509-513,2020)。
そのような中,2023年6月15日に「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律(ゲノム医療法)」が公布された。本法に則り,精神疾患を含む諸疾患を対象として,ゲノム関連データ(オミックスデータを含む)および関連する医療情報の収集と利活用,疾患の病態解明,病態に基づく層別化技術の開発と創薬研究を進めることが期待されている。
ただし,かつて精神疾患が誤った遺伝学的な考えに基づき優生保護法の対象であった点も踏まえ,ゲノム医療の推進のためには,国民の遺伝・ゲノムリテラシーの向上がわが国にとって重要な課題である。ゲノム情報は多様性を生み出す基盤であり,さらに環境の影響を受けて各個人の形質の多様性が形成される。疾患に関連するゲノム情報が明らかになることにより,疾患の有無という多様性(個性)を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことが求められる(障害者差別解消法)。そのためには,患者・家族との双方向性の対話を重ねながら,国民全体がゲノム情報および疾患についてより深く理解し,身近に感じることができる文化と教育を支えるためのシステムの構築が不可欠であろう。
本書は,ゲノム医療法公布を踏まえ,精神疾患のゲノム医療実現に向けて,当事者・家族の思いから始まり,多様なゲノム解析およびオミックス解析手法を用いた取り組み,ゲノム情報に基づくモデル細胞・動物を用いた病態解明について,最新の情報を各専門家にまとめていただいた。
患者・家族の切なる願いである「精神疾患の病態解明」と「根本的治療薬開発」の実現を祈念する次第である。
|