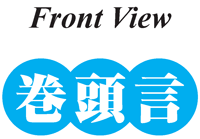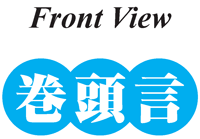ここ数年の遺伝性腫瘍医療の変化はめまぐるしく,まさに激動といえる。治療やリスク管理に関する様々なエビデンスの蓄積はもちろんのこと,それらのエビデンスに基づいた医療保険制度の適用,マルチジーンパネル検査(MGPT)をはじめとする新たな臨床検査の普及など,新たな遺伝性腫瘍医療の臨床実装は着実に進んでいる。それとともに,遺伝性腫瘍医療と一般がん診療の連続性は確実に強くなり,遺伝性腫瘍医療の裾野が広がっている。
なかでも,がんゲノムプロファイリングやコンパニオン診断といった,治療選択を主目的とした遺伝子関連検査は,いまや臨床現場にすっかり浸透し,これらの検査が,受検した患者やその家族にとっての遺伝性腫瘍医療の入り口となる場面も一般的となった。これらの検査の臨床実装がわずかここ5,6年の話であることを考えると,この先5年,あるいは10年の遺伝性腫瘍医療は如何ようになるだろうか。予測することは困難であるにしても,常に新たな視点をもって,患者やその家族にとって最善の遺伝性腫瘍医療を創っていく必要がある。
新しい遺伝性腫瘍医療を創り,臨床実装していくうえでは,技術的な課題だけではなく,倫理的・法的・社会的な課題にも新たな視点からの取り組みが必要である。着床前診断に関する倫理的観点からの議論,未発症者に対する予防医療提供の医療制度上の位置づけや社会的コンセンサスの形成など,取り組むべき課題には事欠かない。すでに海外でなされている取り組みを参考にしつつ,日本の社会的枠組みに沿った医療のかたちを考えなければならない。あるいは,枠組みそのものを新たにつくることを厭わない姿勢も必要だろう。
2023年6月にゲノム医療推進法(通称)が制定され,遺伝医療・ゲノム医療を創り上げるための法的な拠り所ができたことは,遺伝性腫瘍医療においてこのうえない追い風である。この機を逃さず,遺伝性腫瘍医療の提供者と,その恵沢を受けるべき当事者の連携のもと,新たな遺伝性腫瘍医療を創っていく必要がある。本号が,遺伝性腫瘍医療が新たな一歩を踏みだす一助となれば幸いである。
|